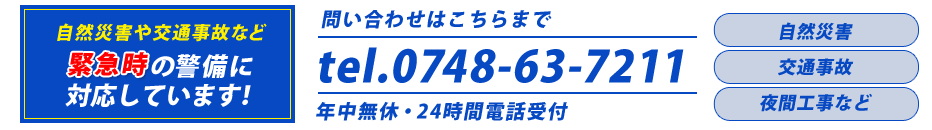2019年09月03日
今回は、警備業と一言で言いましても、色々な警備業務があり、どんなお仕事があるのかをご説明したいと思います。
警備のお仕事は、人々の暮らしに直結する安全や安心を提供する社会的に責任があるお仕事で、お客様の需要に応じ、事故を未然に防いだり適格な誘導により、円滑な流れを作る重要なお仕事です。
みなさんも、警備員さんをいろいろな所で観られると思いますが、警備業には警備業法と言う法律でいろんな法律が定められ、その中で警備業務は区分ごとに大きく4つにわかれ、1号業務、2号業務、3号業務、4号業務に分けられます。
1号業務とは、施設警備業務で、商業施設や空港、ビル、病院などの施設内で行う警備業務やモニター監視、施設内の施錠管理や退出管理、巡回等があります。あと監視カメラやセンサーなどを施設内外に設置して遠方で監視する機械警備業務もこの1号業務に含まれ、セコム様やアルソック様といった会社様がこの機械警備業務では有名どころですね
2号業務とは、弊社がメインで行っています、交通誘導警備業務、雑踏警備業務です。工事現場の交通誘導業務や現場出入りの誘導など、現場により内容は異なりまして、片側交互通行や通行止め、車両の誘導や歩行者、自転車の誘導などがあります。雑踏警備業務では、主にイベントやお祭りなど人が大勢集まる場所の警備業務にあたります。
3号業務とは、輸送警備業務です。現金や貴重品、美術品などの運搬をする際の警備業務や核燃料等の運搬などの警備を行い、輸送する際の盗難や襲撃を未然に防ぐ為の警備業務で現金輸送車に乗っておられる警備員さんもこれにあたります。
4号業務とは、身辺警備業務です。身辺警備とは、ボディーガードとしてよく知られていますが、身近なもので最近では、DV被害対策やストーカー対策といった一般の方からのご依頼で警備するケースも増えているようです。よく政治家や有名な著名人の方のボディーガードをテレビでみますが、まさにそれが身辺警備にあたります。
このように、警備業と一括りでいいましても、色々な警備業務があり、各区分ごとに認定の許可を頂かなければ、その警備業務ができないのですね。
ということで今回は、この辺で
2019年08月17日
早いもので開催地の決定から、もう来年に東京オリンピック、パラリンピックが開催されますね 日本全国の一大イベントで楽しみにしておられる方も非常に多いのではないでしょうか。
日本全国の一大イベントで楽しみにしておられる方も非常に多いのではないでしょうか。
弊社におきましても、さすがに東京管内の警備業務とまではいきませんが、滋賀県でも聖火ランナーが通る為の交通誘導警備業務などの依頼を賜わっております 微力ではございますが、少しでも国を上げての一大イベントに携わらせて頂けることを喜んでいる所でございます。そんな喜びとは裏腹に東京周辺の警備会社様は非常大変だという事を同業者様とのお話の中でよく耳にいたします
微力ではございますが、少しでも国を上げての一大イベントに携わらせて頂けることを喜んでいる所でございます。そんな喜びとは裏腹に東京周辺の警備会社様は非常大変だという事を同業者様とのお話の中でよく耳にいたします
今回の東京オリンピック、パラリンピックでの警備業務の主軸はセコム様と綜合警備保障様がオフィシャルパートナーですが、予定人員の確保でかなり苦労をなされていると言うお話も聞きますし、当初予定されていたコンパクトなオリンピックをコンセプトに算出された警備員数が 1万5千人!だそうで、1万5千人でもびっくりですが、その後に計画の見直しなどがあり、9都道府県で42会場もの設置が決まり、警備員数も大幅に増員となったようです。
過去のオリンピック事例からも見てとれるように、2012年開催のロンドン大会では、世界最大手のG4Sが1万4千人もの警備員の配置予定が、開催直前に4千人しか警備員の配置ができないことが判明し、ニュースにもなっていました。
2016年開催のリオデジャネイロ大会では、1万6千人の警備員数の確保を予定されていましたが、これまた大会直前に人員不足が判明 結局、警備員数、不足のまま大会が開催されたそうです。
過去の事例を見ていましても、会社の規模が違いすぎるとはいえ、同じ警備業務を営んでいる弊社としましても、警備員さんの確保が直前で出来ていなかったという時の事を想像しますとゾーっとしてしまいお気持ちをお察ししてしまいます
とはいえ、今回の東京大会では、2018年4月に、共同企業体のJVも設立されていますし大手警備会社も含め全国で150社あまりの警備会社が参加されるそうで、同じ警備会社としましても、是非、何事もなく成功を収めて頂きたいですし、今大会を機会により一層、警備業の発展を願いたいと思います
2019年08月16日
彦根営業所にて、新人警備スタッフさんの新任教育が始まっています。
お熱い中、熱心に講習を受けて頂きありがとうございます
講師も、現場で役に立つわかりやすい指導を心掛けていますので、
興味のおありの方、求人のご応募賜りますようよろしくお願いいたします


2019年08月08日
これからの警備業の発展を願いまして、過去から現在の日本における警備業の変化について、ご説明させて頂こうと思います
治安が比較的良い日本は、安全面を産業にできるのだろうか?と言う声もあったものの、高度成長が進み、安全への需要が拡大し、年々見直しがなされていると思われます。実際に私共も長年、警備業務に携わらせて頂いておりますが、年を追うごとに色々な場面で警備業の依頼を受け、一般の方々も安全面への認識が非常に高くなってきていると実感いたしております。
警備業が産業として認識され始めたのが、東京オリンピックの選手村の警備業務、大阪万博の警備業務の成功が引き金となったといわれております。しかし、その裏側では、色々な問題点もあったようです。反社会的団体による警備会社設立や警備隊員の犯罪等が多発していたため、昭和47年6月に警備業法が成立されました。 怖い時代があったんですね
この警備業法は、政府(警察庁)の管轄にあり、警備会社は公安委員会の監督の元で、警備業法に基づき警備業務を行わなければなりません。私共は、滋賀県で交通誘導警備業務や雑踏警備業務を行わせていただいてるんですが、滋賀での警備業務は滋賀県公安委員会で認定をもらいます。この認定をもらうのも、結構たいへんで、指導教育責任者と言う免許を持っている方の専任があったり、普段、隊員さんが着用している、警備服の届け出等、色んな書類の提出が必要になります。 そして、すべてをクリアすると、認定書を頂き警備業法に基づき、警備会社として活動できるんです
弊社が行わして頂いている教育も、この警備業法の中で、制定されているんですね。新人警備員さんは警備業務のお仕事に就く前に、バイトさんでも例外なく、 教育を受けて頂かないといけないんです。 教育と言うと、かたぐるしくて嫌 という方もいらっしゃると思いますが、弊社では、初心者でも、わかりやすく丁寧な指導を心がけていますし、また、教育の内容等も常に改善しております。 また、職場内の良好なコミニュケーションと、活気があふれる職場環境を作るため、これからも努力していきたいとおもいます。
それでは、今回はこの辺で